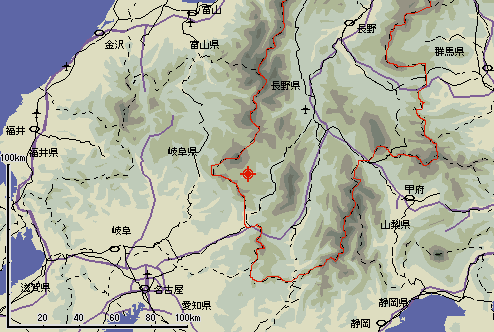路盤は作らず、伐倒木の中でも品質の低い丸太を利用して桟状に組み、その上に軌条を
敷設した。撤収後は丸太を製品として処分できるよう釘など使わず、ホゾ、カスガイを用い
て節約した簡易設計の軌道であった。
一級線、二級線という言い方は、それまで不統一であった全国の規格を昭和28年に林
野庁が改めたもので、森林鉄道を一級線とし、森林軌道を二級線とした。
当初、森林鉄道の運搬方法は、山トロリーと呼ばれる2軸の台車を人力で押し上げ、木
材積載後、その重力によって森林軌道の連絡点まで乗り下げた。そして2台一組の木材
運搬車(運材台車)に木材を積み替え、内燃機関車が貯木場まで運搬していた。
のちに作業軌道まで内燃機関車が入線できるようになると、運材貨車も乗り入れ、山ト
ロリーからの積み替えが省かれ合理化された。しかし最初の頃は、作業軌道では、機関
車は台車を引き上げるだけであった。積車は2台一組の運材台車を4〜5組連結してブレ
ーキ手がそれぞれ乗り込み、重力によって乗り下げを行っていた。機関車は単機で回送
された。戦後、運材貨車に貫通ブレーキが装備されると、機関車が先頭に付き山を上り降
りることが可能となった。こうした機動力の向上と伐採地が山の奥深くなることで、作業軌
道も長くなり、インクラインや2段、3段のループ線を連ねた大規模なものとなっていた。本
線でも有名な煙突を持つ米国製ボルドウィン社のSLは、大型の内燃機関車C4(局形式
DBT10)などの増備によって廃車に追い込まれた。なお、木曾森林鉄道は地元民の足と
して、また、村への物資の輸送手段としても利用された事が特徴的である。王滝村購入の
スクールカー・やまばと号などの入線、運行も許された。


▲山トロリーの乗り下げ ▲王滝村滝越に保存される「ヤマバト号」
しかしながら、木曾森林鉄道も、その大規模さゆえに次第に経営面での限界を呈しはじ
めていた。索道や架線による合理化運材への転換、伐採方法も森林保護から皆伐方式
が間伐方式に改められ、大量運材の時代は終わりを告げようとしていた。基幹の森林鉄
道、軌道も少しずつ縮少されていき、昭和51年の王滝本線廃止を最後に、日本最大と言
われた森林鉄道は、木曾谷から消え去ったのである。
廃止され30年も経とうというのに多くのファンを持つ木曾森林鉄道の魅力は、その規模
や車輌の種類の多さのみならず、地元の人たちの生活に密着していた特別な森林鉄道で
あった事によるのではと考えられる。廃止直前には多くのマスコミにも取り上げられ多くの
人に惜しまれつつの最後であった。このような産業用軌道は他に類をみない。そしていまだ
私達を魅了してやまない。(2004年6月KMC)
●参考資料 (株)ネコ・パブリッシング社刊 西裕之氏著書「木曾谷の森林鉄道」
郷土出版社 「思い出の木曽森林鉄道」